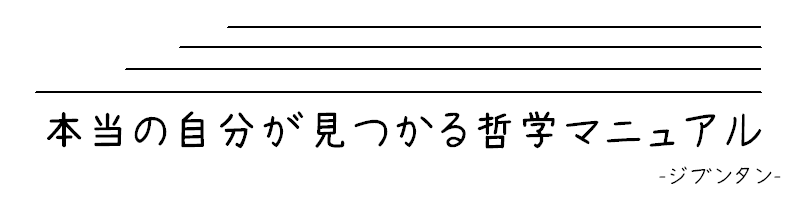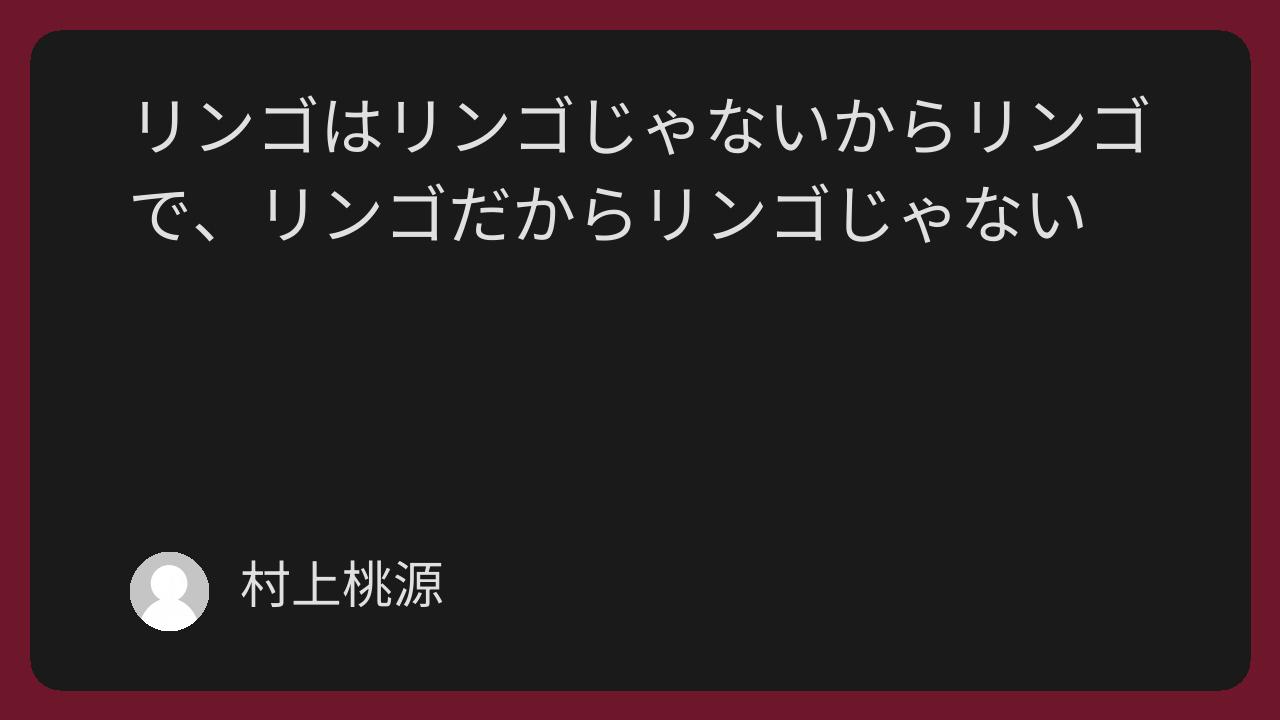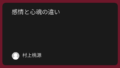リンゴはリンゴではない。
これは心魂をあらわす有力な言葉だが、論理で考える者にとっては矛盾した文章であろう。ここでは論理に傾倒している者にとっても「リンゴはリンゴではない」を理解できるように解説してみたい。
リンゴはリンゴではない
この言葉を説明するためには、世の中にあるすべてのモノをリンゴかリンゴ以外かに分ける必要がある。
リンゴ or リンゴ以外
目の前にリンゴがあるとするなら、その周囲にはリンゴ以外があることになる。テーブルや空気や光エネルギーなど、あらゆるものがリンゴ以外だ。
では、世の中からリンゴ以外がなくなったら、どのようになるだろうか。わたしたちはリンゴを認識できなくなるだろう。リンゴというのは、リンゴ以外からリンゴを切り抜いたものだからだ。
画用紙の色でたとえてもよい。白い画用紙に同じ色の白いペンで丸を描いても白丸は存在できない。白丸が存在するためには白以外の色が必要だ。白以外の画用紙の上でのみ白丸が存在できる。
これを言い換えよう。
白以外の色が白丸をつくっている。白丸が存在するためには、白以外が絶対に必要であり、白と白以外は切り離せないものだ。
リンゴにも同じことが言える。リンゴが存在できるのはリンゴ以外があるからだ。つまり、リンゴという単一のモノは存在せず、【リンゴ+リンゴ以外】という切り分けられていないナニカが存在する。
これをひとことで表現するなら「リンゴは(単独で成り立つ)リンゴではない」となる。
この説明により【リンゴ=非リンゴ】という矛盾する文書の意味をわかってもらえただろう。
リンゴ=非リンゴを心魂で理解する
だが、難しいのはここからだ。
論理的にわかったとしても、心魂でわかるためには長い道のりがある。心魂でわかるということは、常にその存在を肌で感じ続けているということだ。
感覚で言うならば帽子をかぶったときに似ている。頭の上に帽子が乗っている感覚がある。その感覚は歩いているときも、ドリンクを飲むときも、人と会話しているときも感じられる。
それと同様に、リンゴはリンゴではないという感覚を、日常で感じ続けたとき、ようやく心魂でわかったと言えるわけだ。
何ごとも【リンゴ=非リンゴ】であるし【A=非A】なのだから、物体にしろ概念にしろ、何かに触れている間は【A=非A】の感覚を味わうことになる。
するとAと非Aの境界線が曖昧になり、なんだか物事が1つのものに感じられる。良いと悪いが1つになり、加害と被害が1つになり、少ないと多いが1つになるのだ。
まとめ
リンゴが存在するためにはリンゴ以外が必要である。リンゴ単独ではリンゴは成立しない。というのが今回の内容であった。それはつまるところ世界の根っこは非分割であるということだ。リンゴとリンゴ以外はもともと分割されていない。1つのものであった。我々人間があとから分割したのである。
次回は──着地しない受けとめかた──について解説していきたい。