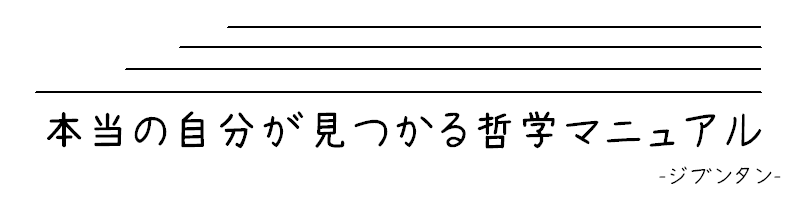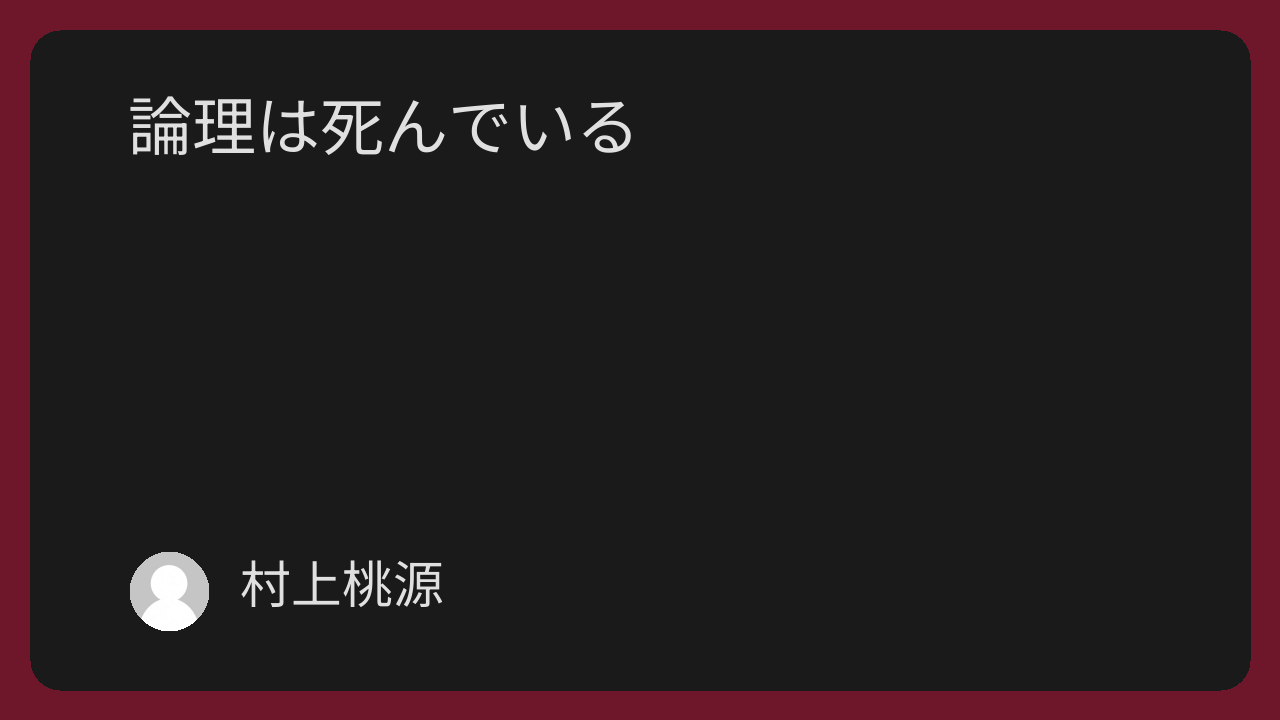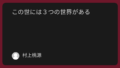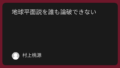論理は死んでいる。
……と、いきなり書籍タイトルのような書き始めになってしまったが、論理的に考える人ならご理解いただけるであろう。論理的には論理は死んでいるのである。
前回、この世には3つの世界があるにてこの世は物理の世界、論理の世界、心魂の世界の3種類に分けられるといった話しをした。今回はそれを踏まえた上で、なぜ論理は死んでいるのか説明したいと思う。
論理は死んでいる
論理とは何か
論理というのは定義や決め事、計算の世界だ。ひとつのことを”1と表すのだ”と定義し、その上で1と1を足し合わせたら2になるという計算をする。
数学以外にも論理はある。というよりも、社会活動の大部分は論理によってつくられていると言ったほうが正確だ。
根拠:雇用契約を結んだ
結果:だから出社する
または
根拠:お金を支払った
結果:だから商品を受け取った
というように社会活動は「AならばB」「AだからB」という論理に支えられている。
倫理で考えると”私”がいなくなる
仏教には無我(むが)という言葉がある。シンプルに言うと”私はいない”ということになるが、無我の意味は僧侶によっても捉え方や表現の仕方が違うものだ。アートマン(輪廻転生を繰り返す魂)はないという意味で使われたり、物事は単独で成り立たないという意味で使われたりもする。
ここでは物事は単独で成り立たないことを無我と書くことにしよう。
論理で考えると無我は事実である。”私”が存在するためには、”私”と”私以外”に境界線が必要だ。真っ白のキャンバスに描いてある”私以外”を消したら”私”が浮かび上がってくる構造である。
たとえば、私とAさんが喧嘩をしたとする。私がAさんと喧嘩できたのはAさんが近くに存在し、Aさんが喧嘩に応じたからだ。もっと言えば、Aさんが私を怒らせる振る舞いをしたから、そして私が怒ったから喧嘩になった。
ではなぜ私が怒りを感じたかというと、そういう価値観を持っていたからである。私の価値観は生まれたときの環境、家族の接し方や金銭事情、学校でどんな人と出会ったかなど、過去のすべてに影響を受けている。
私というものは単独では成立せず、いまいる私は過去から連続した1つであるし、私以外によってつくられた私なのだ。
白い画用紙のイメージに置き換えてみよう。私以外の部分を黒で塗りつぶすと、白く残っている部分が私になる。私を塗った(私がいる)のではなく、塗り残しのことを私と呼んでいる(私がいない)のだ。
このように論理的には無我が事実ということになる。
“私”がいると思って生きている
論理的には私がいないのに、私たちは”私がいる”と思って生きている。論理的な事実を無視して生活しているわけだ。
なぜ事実を無視するのだろうか。その理由は世界の根底にあるのが論理ではなく心魂だからである。私たちは心魂という地上に立ち、空中に論理というルールを構築した。
何でも正しいし、何も正しくないし、すべて間違っているし、すべて間違っていない。縛るものがなく自由。なぜなら論理は遊びだから(論理は死んでいるから)だ。
根っこにはいつも心魂がある。論理というのは、表面上だけ取り繕ったハリボテだ。
まとめ
やや難しい内容となったが理解していただけたのではないだろうか。論理が遊びである、ということを身にしみて理解するためには、もっと具体的な事例があったほうがいいと思っている。
次回は、具体的な例を使って論理について解説したい。