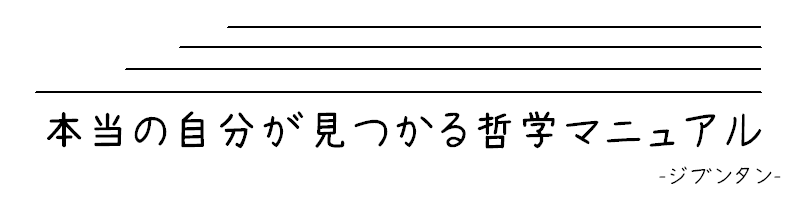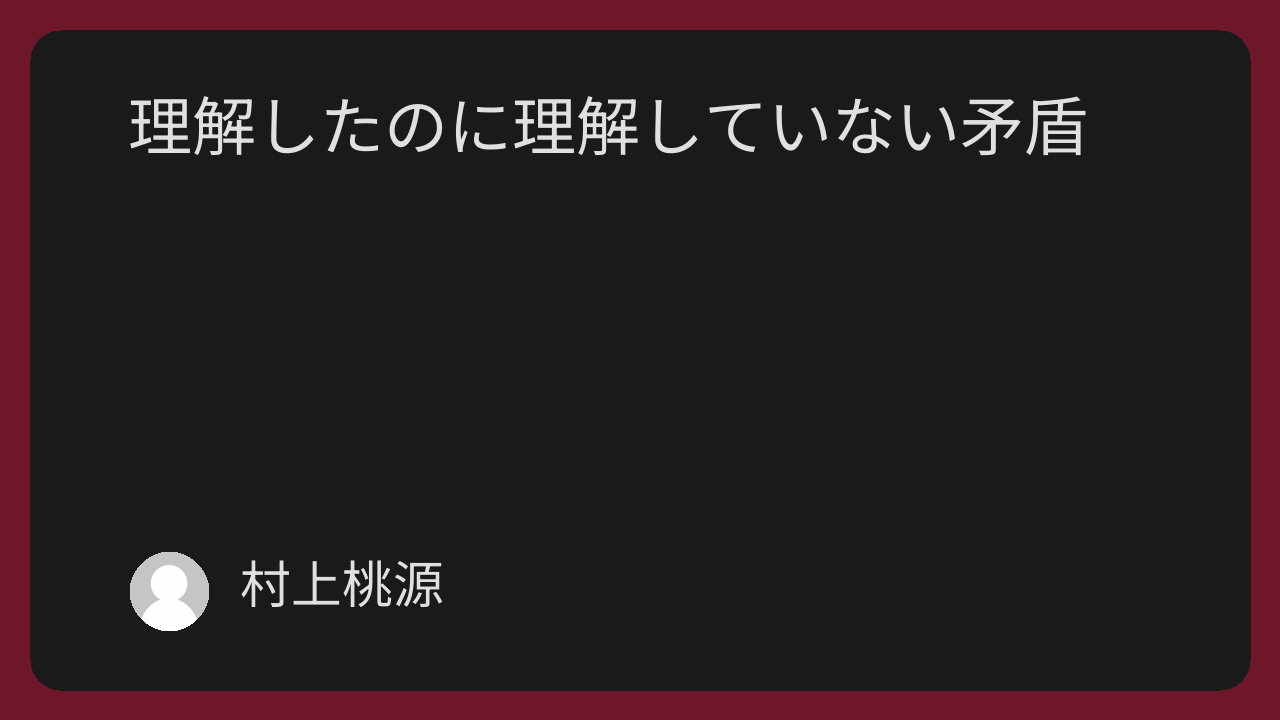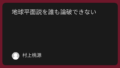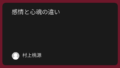「理解したのに理解していない」という文章は論理的に矛盾している。
前回、地球平面説を誰も論破できないで解説したように我々は矛盾の中で暮らしている。論理ではわかっているが心魂ではわかっていない、という状態だ。
このページでは具体的なシチュエーションを例にして理解の矛盾を解説していきたい。
わかっているのに腹を立てる
小雨が降っているけれど傘をささない、という選択をするときがある。少しの移動だから傘を使わずに走るシチュエーションだ。このとき雨に濡れてもイライラは少ない。
イライラが少ない理由は、雨で濡れることを論理と心魂の両方で理解しているからである。雨に当たると濡れるという物理法則の論理はもちろんのこと、心魂の世界でも雨に濡れることをわかっている。
では、こんどは会社で嫌味を言われる、というシチュエーションを考えてみよう。嫌味を言われたときにイライラしたり悲しくなったりネガティブな感情になる。しかし、我々は論理的にはわかっているはずだ。
どんな組織にも必ず嫌な人間が現れるし、人類80億人の中には必ず悪意を持った人、嘘を付く人、故意に攻撃をする人、不和を喜ぶ人がいる。
嫌な相手がいることを論理的には完全に理解しているし、避けられないことだとわかっている。さらに言うならば「あの人は嫌味を言うタイプの人間だから」とわかっていることさえある。
わかった上で仕事場に向かうのだが、心魂ではわかっていないため雨のときと違って感情がネガティブに働く。
本来であれば雨よりも嫌味のほうがマシなのだ。雨は物理的に乾く時間が必要なのに対し、嫌味は鼓膜を揺らしただけなのだから。
しかし実際は心魂で理解できていない嫌味のほうにダメージを受けてしまう。
モスバーカーとマクドナルド
もう1度、モスバーカーとマクドナルドの話をしよう。
モスが大好きなAさん、マックが大好きなBさん。お互いがデータを使って論理的に「自分の好物のほうが美味しい!」とプレゼンをしても意見は変わらないという話しをした。各々の体験によって好物が決まるのだからデータを提示されて好物が変化しないのは当然である。
これまで論理は遊びだ、論理は死んでいる、ということを言ってきたが、日々の生活で論理が遊びだと体感するのは難しい。遊びであるはずの論理を、さも正しさの根底のように感じてしまう。
どんなに話し合っても無駄なことがある。それはわかっている。相手に悪気がないとわかっている。仕方のないことだとわかっている。が、すんなりと受け入れられないのは根底に論理が正しいという思いがあるからではないだろうか。
わたしが例を変えて似たような話しを繰り返すのは論理が遊びだと体感してもらうためだ。そうすることで世界の見え方が変化し、本当の自分を見つける近道があらわれる。
まとめ
論理的には当たり前だと思っても、心魂で体感していないことはすんなりと受け入れられない。世界の根底には心魂があり、その上に遊びとしての論理があるのだ。
では心魂とは何であろうか。よくある誤解は、心魂を感情だと考えてしまうことだ。感情というのは肉体の生理作用である。脳へ電気刺激を与えたり、薬剤を注入することで感情は書き換え可能。つまり、3つの世界(心魂、論理、物理)で言えば、物理法則に属するものが感情だ。
さて次回は心魂についてより詳しくお伝えしたいと思う。お時間のあるかたはお付き合い願いたい。